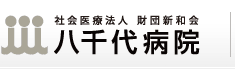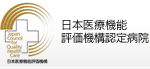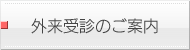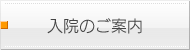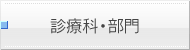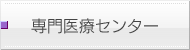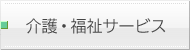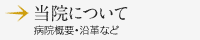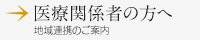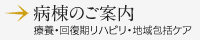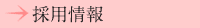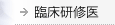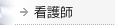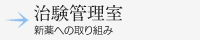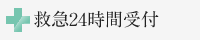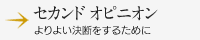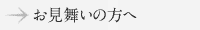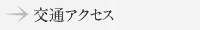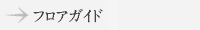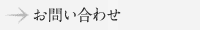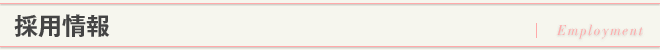臨床研修医
■研修修了者の声
研修を終了して
Aさんからの研修レポート | 病理医 Report-001
私は平成20年に名古屋大学を卒業し、安城市にあります八千代病院で2年間の初期研修を修了致しました。現在は名大病院病理部にて病理医として働いております。
八千代病院は安城市の北部に位置し、病床数320床の地域の基幹病院の一つです。臨床研修指定病院としては小規模ではありますが、40年程前から卒後ローテート研修が行われており、その歴史は長いです。
2年間の私の八千代病院での日々を振り返りつつ、「研修報告」をしたいと思います。私個人の経験を通して綴られた文章ですので、主観的な点も多々あると思いますが御許しください。
私の研修生活は4ヶ月の外科研修からはじまりました。一年目の主な仕事は、朝の外来処置枠、病棟回診、手術の麻酔当番や助手でした。少し余裕が出てくるとエコー検査や透視検査を教わったりしていました。初めてだったということもあり、気づけば一日が終わっているという日々であったと思います。
最後の月には局麻手術やアッペンの手術をやらせていただきました。私の初アッペンでは「こんなきれいなアッペンは二度と無いぞ」と言われた程、軽いものであった事が印象に残っております。
その後は小児科、整形外科にて研修しました。どちらも常勤の先生は二人であり、小所帯ではありましたが、ローテートしている研修医は私一人でしたので、その分濃密な研修を行うことができました。整形外科では観血的骨折整復術をはじめ、色々な手術をさせていただきました。
小児科では生後しばらく経った、ムチムチしてきた頃の赤ちゃんのルート確保には苦労しました。思えば一か月の研修の間で一回も成功していないかもしれません。
一年目の後半から二年目の初めにかけては内科を半年間まわりました。八千代病院の特色として、内科研修は細分化されておらず、ざっくりと「内科」ローテートです。午前中は腹部エコー検査、胃カメラ検査を行い、午後は心カテ、合間に気胸の患者さんを発見すればトロッカーを入れさせてもらったり、CV挿入したり。医師にとって必要な基本手技を身に付けるチャンスを逃さないためにいつもアンテナを張っていました。毎朝その日の検査予定をチェックし、やりたい症例があれば主治医へcall、大抵の場合は「いいよ。」と言っていただけました。
内科ローテート中は入院患者もけっこう担当させていただきました。自分が救急外来から入院させた患者さんや、研修医に適当と思われる患者さんを振りわけてもらいました。第一主治医であり、オーダー権もあり、非常に勉強になりました。
その次は産婦人科をまわりました。この産婦人科をまわっている途中で、私自身が身体を壊し、半年ほど研修を休んでおりました。そのうち4ヶ月ほどは患者として八千代病院に入院しておりました。この間に病ありきで自分の進路を考え直し、外科医から病理医へ進路を変更しました。
復帰後は病理部においてその日でき上がる標本を毎日診るようにして、病理医としてのトレーニングをはじめつつ、脳外科病棟の病棟医として働いたりしました。
2年間通して行い、最も力を入れていたと言ってもいいのが救急外来の仕事です。救急外来では研修医が主役でした。八千代病院は二次救急病院でしたが、救外に来る患者は基本的にすべて自分で診ます。入院決定や入院時オーダーもある程度任されます。自分の色を出せる場でもあり、勉強したことを現場で実践したりしていました。おかげさまで度胸はついたと思います。今、当直バイトをしていてもビクビクすることなくできるのはここでの経験のおかげだと思います。
2年間の私の研修生活を簡単に振り返ってみました。思うに、八千代病院は研修医に対しとても「懐が深い」病院であると思います。他院のことは分かりませんので比べることはできませんが、研修医にあれだけの裁量権、責任を与えてくれる病院はあまり無いと思います。おかげさまで主体的な良い研修を行えたと思います。
今後の八千代病院の更なる発展を願いつつ私の「研修報告」を終わらせていただきます。
八千代病院で臨床研修を受けた卒後5年目の内科医
Bさんからの研修レポート | 内科医 Report-002
私が何故この病院で内科を目指し、研修したか…ですが単純です。手技の習得が異常に早いと感じたからです。私は消化器内科医ですが、研修3ヵ月目で中心静脈(CV)の穿刺を始めました。そいて1年目で胃カメラ検査を始め、2年目で大腸カメラ検査を始め、3年目で十二指腸カメラを使って総胆管結石の治療を始めました。また胆管治療を始めればPTBDやPTGBD(経皮的胆道-胆嚢ドレナージ)も並行して始める事になります。これだけで大抵の消化器疾患は大体治療が出来ます。もちろん指導もきちんと受けることができ、行き詰まればいろいろと補ってもらっています。(余談ですが当院の研修医は希望が何科であろうと、胃カメラ検査の習得を目指しています)
当院は大規模病院ではないので専門分野以外の疾患も診る事があります。すなわち誰でも総合内科的と言えるかもしれません。消化器内科でも心不全や肺炎、糖尿病、甲状腺疾患、急性or慢性腎不全、尿路感染症などは診ています。
当院は医師の数が50人程度なので全ての医師の顔がわかり気楽に話ができ、患者さんのことで困った時にすぐに相談に乗ってもらったり指導を受けたりできます。またMDCT(64列)はもちろんMRIでさえ緊急でも気軽に依頼できるので、大学病院では考えられない速度で検査結果が得られます。そして画像を医局のPACSモニターでみながら皆でディスカッションをして方針決定のような良い流れがあります。
当院も他と同じく医師不足気味で、研修医に早く戦力になってもらえるようガンガン育てます。研修内容の自由度も高く、伸びられる研修医にはどんどん成長してもらおうと思います。研修医の能力の平均化など考えていませんが、少人数なので目が行き届きやすくその必要が無いからです。Common Disease は本当に沢山診られます。その中に埋もれている稀な疾患を見つけ胸を躍らせる事もしばしばです。
当院で研修希望される方の理想像は ①2年間仕事に没頭出来る人 ②頭より先に体の動く人、辺りかと思います。この2年を本気で頑張れば群を抜いた実践力と肝っ玉の太さを持つ医師になります。私は当院2年間をそれなりに仕事に没頭した結果、お金を使う暇も無く、2年で900万以上貯まってしまいました(笑)。
研修を終了して
Cさんからの研修レポート | 内科医 Report-003
■八千代病院との出会い
学生時代に大病院、有名研修病院を北は栃木県、西は岡山まで10箇所あまり見学してきた。どの病院もすばらしい設備と多くの研修医がいた。しかし大学からのカリキュラムの一貫で1ヵ月半をすごした病院は医師数30人ぐらいで、1つのフロアーに全部の科の先生が机を並べ一緒に過ごしていた。科の間のコンサルトは食堂や医局の休憩室で普通に会話をしながらできる。後で書類は書くけれども。他科に転科した患者のその後もすぐにわかる。大病院では同僚医師の顔を全て把握するのは難しいし、コンサルトも大学と同じように堅苦しい文書を書かなければならない。小規模の病院の良いところを見ることができた。このような病院では研修医も研修医としてよりは戦力としてみなされ、見学よりは実践を求められる。大病院の症例の豊富さは魅力だが、研修医にできることは限られる。実力をつけるなら小さな病院だと判断し、その後は100床から300床ぐらいの病院で研修医が元気な病院を探して回った。その中で出会ったのが同級生から紹介された八千代病院であった。
■研修内容
研修は満足のいくものであった。なんでもまずやってみる。もちろん監督の下で。厚生労働省の研修医の経験すべき項目は1年でほとんどこなしていた。一応身分は研修医なので監督のもとでの実践であるが、ほとんど1人でできてしまうようになっている。超音波検査、内視鏡検査、麻酔管理、気管切開などの小手術、虫垂切除、アテローマ切除、分娩、帝王切開、卵巣切除、子宮全摘など、やる気さえあれば何でもしっかり勉強した上であれば実践できる。大きな病院へ行った大学の同級生の話を聞いていると八千代病院へ来て本当に良かったと思えるようになる。
■日常生活
日常生活はこんなかんじである。当直は週に1から2回、月に7回前後。初めの頃は早く仕事を覚えたかったので、上の先生の当直の時には救急外来の診察台の上に寝て、勉強になる症例の時には直ぐに起こしてもらえるようにしていた。吐血の緊急内視鏡、脱臼の整復、外傷の縫合、心肺蘇生なども、何度かさせて頂いた。なんでもない日は病棟を散歩し、かわった症例がないか探して回ったりした。興味を引く症例は他科でも一緒に診せて貰ったりした。大病院には症例数はかなわないかもしれないが、自ら見られる症例を一つ一つ大切にし、集めていけば意外といろいろな症例をみられる。また自分の体力に合わせて、元気のある日は自主的に病院に残っていれば、何かのチャンスがめぐってくるかもしれないから。
■休日
普通に映画を見に行ったり、夏休みには海外旅行へも行きました。病院に就職する前は研修医で海外旅行など無理だと思っていたが、ローテートの間でイタリアへ1週間の旅行に行かせていただきました。
■最後に
まだ研修病院を決めかねている人には、一度来院されて見学されることをお勧めします。自分で見て、体験して貰えれば、必ず八千代病院の良いところが分かると思います。
研修を終了して
Dさんからの研修レポート | 外科医 Report-004
3月末。医師国家試験の発表後、数日と立たないうちに病院の社宅へと引っ越し、右も左もわからないまま臨床研修がスタートされたことがつい先日のように思い出されます。
八千代病院は私が就職した平成17年5月に旧病院から数百メートルの現在地に移転しました。病床数320床(内、療養病棟52床、回復リハビリテーション病棟52床)と規模は小さいながらも、100年以上にわたり歴史を持つ地域に根付いた病院であり、臨床研修制度開始前よりスーパーローテートの先駆けを実践し、第一外科前教授の二村先生や現教授の梛野先生も研修された由緒ある病院でもあります。
「なぜ八千代病院を選んだの?」よく同期からもこのような質問をされました。いわゆる名大系列と呼ばれる病院の中には、全国から研修医が集まるような大病院は幾つかありますし、この病院しか選択肢がなかった訳でもありません。学生時代、それらの病院を見学させていただきましたが、当院は研修医の病院における役割が非常に大きく、症例に触れる機会が多いことに魅力を感じました。なによりもこの病院の研修医の責任感・充実感にあふれる姿をみて、他の病院との違いを感じのこの病院を選びました。
私の同期は他に1名でしたが、臨床研修制度開始後は年平均3名が研修を行っています。研修に関しては厚生労働省の指定範囲内で、原則自由にローテートが可能です。研修内容としてはまず最初の1ヶ月間、外科にて基本手技を学び、その後各科をローテートします。私の場合は2年目の10月より外科にて準スタッフとして研修を行い、3年目を迎えた現在そのまま当院職員として在籍しています。
研修医は見学よりは実践を求められます。やる気さえあれば何でも実践できます。外科に関しては局麻手術、気管切開、虫垂切除、鼠径ヘルニア、VATS、ラパコレ、腸管吻合などなど。その他の科でも観血的骨折整復術、帝王切開、子宮全摘、筋腫核出術、上部消化管内視鏡も200例以上経験させていただきました。
各科や病棟からはローテートとは関係なく、診察を依頼されることもしばしばあります。研修初期に先輩から教わった「頼まれたことは原則断らない。断ったらその機会は2度と自分に来ない。そして2度と頼まれなくなる」との言葉は私に衝撃を与えました。逆にいえば断らなければ、また次の症例にめぐり合うことが可能となるわけです。訴訟も多い昨今ですので、一人ですべて何とかしようと意固地になったり、無謀になったりはしません。しかし一つ一つの症例や手技を探し出し、考える、調べて悩む。与えられるだけでなく、自分が主となり上級医と共に解決するプロセスは大変貴重でした。
研修医が前面に立つ救急外来。回数は平均月に6-8回程度。2次救急ですが、入院となった場合はそのまま自分が主治医となり、場合によっては手術し、退院まで一貫して患者を診ることが可能です。そのような患者がようやく退院までたどり着いたときには大きな充実感に満たされます。入院させて各科にお任せという病院も多いようですが、このような経験は当院のような規模の小さな病院だからこそ可能であると思います。2年間での主治医として経験した症例(全麻・腰麻の手術件数60件、退院サマリー170件)の一つ一つが鮮明に記憶され、私の財産となっています。
定期的な勉強会はありませんが、週に一度の救急外来患者の症例検討や、各科からの講義も適宜行われます。とはいえ、各科の敷居は低いので、その場その場の困った症例について気軽にコンサルト可能です。
私に関しては当初の志望どおり、外科を専攻させていただいております。内視鏡の利用により内科的に治療可能な分野も多くなってきてはいますが、やはり'治す'切り札として外科は大変魅力のある分野です。5月からは外来診療を担当させていただき、新たな活躍の場ができたことに大きな期待と喜びを感じております。
いかにフットワークよく働ける医者になるかは、研修の仕方で大きく変わるものと考えます。医師としての経験年数を経ても、この研修で培ったものを生かしていこうと思います。